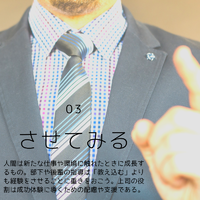2012年01月04日
一朝入魂(285)

昨日、チラリとではあるが映画「男はつらいよ」を見る機会があった。
1980年公開の「寅次郎かもめ歌」偶然にも私が生まれた年である。
ここ数年毎年のように「正月らしさがない」とぼやいているが
寅さんエンディングおきまりの正月風景を見て
「あぁ、お正月なんだなぁ」と感じることができたような気がする。
沖縄タイムスの正月号に、あるファミリーの40年前と今の沖縄の
正月の過ごし方の変化が特集されていた。晴れ着を着て家族で
写真を撮った40年前の正月と比べ今の正月はだいぶライトにな
っている。
寅さんと、このファミリーを見てふと感じる。
そう、正月らしさって、受動的なものではなく、もっと能動的に
感じる努力をするものなのかもしれない。「ハレ」と「ケ」の区別が
薄まりつつある時代だからこそ、特に強い意識が必要だろう。
日本人の伝統的な世界観のひとつに「ハレとケ」。

ハレ(晴れ)は儀礼や祭、年中行事などの「非日常」、
ケ(褻)はふだんの生活である「日常」。
私たち日本人は、ハレの場において、衣食住や振る舞い、
言葉遣いなどを、ケとは画然と区別してきた文化がある。
私の場合、節目節目の行事に無頓着な家庭に育ったこと
もあり年中行事とこれまでほとんど関わることなく生きてきた。
しかし、社会人になり、結婚して諸行事と接していると、この
ハレとケの画然とした区別に大きな意味があり、その中に
私達の日々の営みと成長があるのだと感じるようになった。
特にお正月にお雑煮を食べたり、今日のような年始会に出席
すると強く感じる。
諸説あるそうだが、私は「ハレ」と「ケ」はある種の循環モデルだ
という説に心惹かれる。
私達の日常生活を営むための「ケ」のエネルギーが枯渇するのが
「ケガレ(褻・枯れ)」であり、「ケガレ」は「ハレ」の祭事を通じて回復
するという考え方だ。個人的にはお正月の「ハレ」にそのパワーが
強く秘められている気がする。
今日から仕事始めという会社も多いだろう。
職場の仲間と「ケ」の力をしっかり蓄えて欲しい。
Posted by 大城勝太 at 09:51│Comments(0)
│旧コラム:一朝入魂