2013年10月29日
一朝入魂(492)
先週の土曜日、県立博物館美術館の講堂で開かれた
「ストレスとうつを知る」セミナーに参加してきた。

県立総合精神保健福祉センターの仲本晴男所長と
県内外でコミュニケーショントレーナーとして活躍す
る豊田麻琴さんが講演し、ストレスフルに陥りがちの
現代社会の特徴やその対処法について話を聴くこと
ができた。
まず、豊田さんは、
①インターネットの普及や
②グローバリゼーションの増加
③雇用の多様化で
ストレスが増える傾向にあると指摘。
一例として
ネットの普及で顧客対応の中心が
電話からネットに移行。
電話であれば、その様子から
きついクレームを受けているとか
対応に困っているという状況を
周りが察して声をことができた。
しかし、メールの場合はクレームも
難しい対応もすべて一人抱え込み、
周りから困っている様子が見えづらく
声かけの機会を逸しやすい。逸している
というのである。それが結果として
メンタル不全の増加を招いている一因
と紹介。
メンタル不全が増えることで、
まず
①労働日数が喪失。
②スタッフの欠員で仕事のミスが増加。
仕事ができる人とそうでない人の業務負担の不均衡が生まれ、
③労災認定が増加
すると指摘。
それは、本人にとっても企業にとっても社会にとっても
大きなロスになる。
そうならないために、相談をしやすい仕組みづくりや
相談を受ける側、つまり管理職の「聴く力」「声かけ」の
スキルを向上させる必要性を強調した。
例えば、叱る時はその人の人格や価値観ではなく
その人の行動を叱る。
褒める時は、その人の行動よりも人格や価値観を褒める
という具合に、声かけ一つでスタッフの受ける印象、
ひいては受けるストレスがだいぶ違うということ。
そして、仲本所長は専門の認知行動療法の有効性を強調。
ストレスは適度に必要と強調した上で、そのストレスの
受け止め方を、ネガティブなものではく、前向きなもの
にすることによってストレスの量を自分でコントロール
することができると訴えた。
詳細は明日以降のコラムで触れたい。
「ストレスとうつを知る」セミナーに参加してきた。

県立総合精神保健福祉センターの仲本晴男所長と
県内外でコミュニケーショントレーナーとして活躍す
る豊田麻琴さんが講演し、ストレスフルに陥りがちの
現代社会の特徴やその対処法について話を聴くこと
ができた。
まず、豊田さんは、
①インターネットの普及や
②グローバリゼーションの増加
③雇用の多様化で
ストレスが増える傾向にあると指摘。
一例として
ネットの普及で顧客対応の中心が
電話からネットに移行。
電話であれば、その様子から
きついクレームを受けているとか
対応に困っているという状況を
周りが察して声をことができた。
しかし、メールの場合はクレームも
難しい対応もすべて一人抱え込み、
周りから困っている様子が見えづらく
声かけの機会を逸しやすい。逸している
というのである。それが結果として
メンタル不全の増加を招いている一因
と紹介。
メンタル不全が増えることで、
まず
①労働日数が喪失。
②スタッフの欠員で仕事のミスが増加。
仕事ができる人とそうでない人の業務負担の不均衡が生まれ、
③労災認定が増加
すると指摘。
それは、本人にとっても企業にとっても社会にとっても
大きなロスになる。
そうならないために、相談をしやすい仕組みづくりや
相談を受ける側、つまり管理職の「聴く力」「声かけ」の
スキルを向上させる必要性を強調した。
例えば、叱る時はその人の人格や価値観ではなく
その人の行動を叱る。
褒める時は、その人の行動よりも人格や価値観を褒める
という具合に、声かけ一つでスタッフの受ける印象、
ひいては受けるストレスがだいぶ違うということ。
そして、仲本所長は専門の認知行動療法の有効性を強調。
ストレスは適度に必要と強調した上で、そのストレスの
受け止め方を、ネガティブなものではく、前向きなもの
にすることによってストレスの量を自分でコントロール
することができると訴えた。
詳細は明日以降のコラムで触れたい。
Posted by 大城勝太 at 06:37│Comments(0)
│旧コラム:一朝入魂









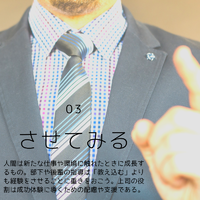









書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。