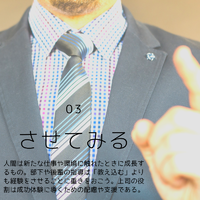2018年11月23日
祝日?祭日?祝祭日?〜表現の部屋(9)〜
さて、今日は勤労感謝の日。

さて今日のような旗日のことを「祝日」
と言ったり「祭日」と言ったり、
まとめて「祝祭日」と言ったりしますが
実際どっちが正しいのだろう?って
不思議に思ったことはありませんか?
では、祝日と祭日の違いをおさらいしましょう。
まずは「祝日」の定義。これは、建国や独立など、
その国の大きな出来事や記念日を国が制定した日で、
法的根拠は1948年に制定された
「国民の祝日に関する法律」にあります。
続いて「祭日」
皇室の祭典や神社のお祭りなどをさし、かつては、
皇室祭祀令という法令で祭日と定められていました。
しかし、宗教的意味合いの強いということもあり、
戦後GHQの指導で1947年に廃止されました。
なので現在では「祭日」に法的根拠はありません。
また宗教的な意味合いも強いということで、放送では
「祝祭日」や「祭日」という言葉は使わず
「祝日」という言葉を使います。
ちなみに今日勤労感謝の日は、もともと「新嘗祭」が起源。
天皇が収穫した作物を神様にお供えし、五穀豊穣を感謝する
儀式です。戦前は「祭日」とされていたこの日も、現在では
勤労感謝の日という「祝日」に引き継がれたというわけです。
同じような理由で、11月3日の「明治節」は文化の日として
祝日に引き継がれ2月11日の「紀元節」は建国記念日として
祝日となっています。もちろん、10月17日の神嘗祭のように
引き継がれずに廃止になった祭日もあります。
コラムを〆る前にもう一つ、うんちくを。
お気付きの方も多いと思いますが
今日のようにかつて祭日だった「祝日」は
ハッピーマンデー制度が導入されません。
説明の必要はりませんね。その背景を考えれば当然ですね。
と、いうことで、
今日は「働く」こと「働ける」喜びに感謝するのはもちろん
本来の意味である五穀豊穣への感謝も忘れないようにしましょう。

さて今日のような旗日のことを「祝日」
と言ったり「祭日」と言ったり、
まとめて「祝祭日」と言ったりしますが
実際どっちが正しいのだろう?って
不思議に思ったことはありませんか?
では、祝日と祭日の違いをおさらいしましょう。
まずは「祝日」の定義。これは、建国や独立など、
その国の大きな出来事や記念日を国が制定した日で、
法的根拠は1948年に制定された
「国民の祝日に関する法律」にあります。
続いて「祭日」
皇室の祭典や神社のお祭りなどをさし、かつては、
皇室祭祀令という法令で祭日と定められていました。
しかし、宗教的意味合いの強いということもあり、
戦後GHQの指導で1947年に廃止されました。
なので現在では「祭日」に法的根拠はありません。
また宗教的な意味合いも強いということで、放送では
「祝祭日」や「祭日」という言葉は使わず
「祝日」という言葉を使います。
ちなみに今日勤労感謝の日は、もともと「新嘗祭」が起源。
天皇が収穫した作物を神様にお供えし、五穀豊穣を感謝する
儀式です。戦前は「祭日」とされていたこの日も、現在では
勤労感謝の日という「祝日」に引き継がれたというわけです。
同じような理由で、11月3日の「明治節」は文化の日として
祝日に引き継がれ2月11日の「紀元節」は建国記念日として
祝日となっています。もちろん、10月17日の神嘗祭のように
引き継がれずに廃止になった祭日もあります。
コラムを〆る前にもう一つ、うんちくを。
お気付きの方も多いと思いますが
今日のようにかつて祭日だった「祝日」は
ハッピーマンデー制度が導入されません。
説明の必要はりませんね。その背景を考えれば当然ですね。
と、いうことで、
今日は「働く」こと「働ける」喜びに感謝するのはもちろん
本来の意味である五穀豊穣への感謝も忘れないようにしましょう。
Posted by 大城勝太 at 13:31│Comments(0)
│表現の部屋〜ことば編〜